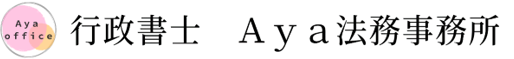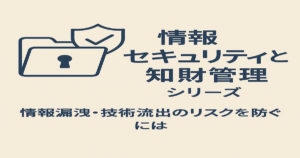AI学習と著作権、米国で2200億円和解が示す新たな課題
目次
- 訴えの経緯 — 作家たちはなぜ提訴に踏み切ったのか?
- 裁判の論点 — フェアユースか?違法使用か?
- 和解に至った経緯 — なぜ2200億円という巨額になったのか?
- 今後の著作権侵害裁判に与える影響 — AI時代の新たな地平
- 日本への影響 — 私たちの創作活動とどう向き合うか?
- 中小クリエイター・個人事業者はどう対応すべき?
- まとめと行動喚起
訴えの経緯 — 作家たちはなぜ提訴に踏み切ったのか?
米新興AI企業Anthropicは、ChatGPTの対抗馬とされる生成AI「Claude(クロード)」を開発し、急速に存在感を高めてきました。そうした中、2024年に複数の著名作家がカリフォルニア州連邦地裁へ提訴。自らの著作物が権利者の許可なくAI学習に使われたとして、著作権侵害を主張しました。
訴状とその後の手続で明らかになった重要点は、いわゆるシャドウライブラリ(LibGen/Library GenesisやPirate Library Mirror等)から入手されたとされる大量の海賊版書籍の存在です。これらが学習データとして保存・利用されていた疑いが濃く、争点は一気に「フェアユース(公正利用)の範囲内か/違法使用か」へと絞り込まれていきました。
裁判の論点 — フェアユースか?違法使用か?
AIの「学習に使うだけ」は合法か?
AI開発では、インターネットや各種コーパスからテキストを取得して学習させるのが一般的です。これに対し著作権者が異議を唱える場合、必ずといってよいほど焦点となるのがフェアユースです。Anthropic側はおおむね「学習目的に限るならばフェアユースに該当し得る」との立場を示し、学習の自由を強調しました。
しかし裁判所は、線引きを明確にしました。合法に購入した書籍を解析目的で用いること自体は、状況次第でフェアユースに該当する余地がある一方、LibGenなどからの海賊版を大量にダウンロード・保存する行為は、明白な違法複製であってフェアユースの範囲外と判断。学習目的であっても、出所の違法性は免罪符にならない、という強いメッセージが示されました。
この判断は、AI開発における「学習の自由」と、著作権者の「利用許諾権」とのバランスをどこで取るかという根源的問題を、具体的事実関係のもとで可視化した点に大きな意義があります。
和解に至った経緯 — なぜ2200億円という巨額になったのか?
「違法ダウンロード」という“逃げられない事実”
和解交渉の中で特に重視されたのは、Anthropic側が利用していた海賊版データの規模と、その違法性を裏付ける証拠の存在でした。実際に使用されていた書籍データは700万冊以上にのぼり、保管されていたサーバーの中身からは「明確な違法コピー」と判定される複製物が多数確認されました。
こうした証拠により、Anthropicが主張していた「フェアユース」の適用は一部にしか認められず、裁判所の判断を受けて同社は不利な立場に追い込まれました。その結果、Anthropicは最大で15億ドル(日本円で約2200億円)という巨額の和解金を支払うことに同意し、訴訟を終結させる道を選択したのです。
海賊版データの破棄などの措置も含まれ、「過去の行為の清算」に軸足を置いた決着となりました。
作家側も“早期の補償”を選んだ理由
一方の原告側も、長期化する法廷闘争よりも、被害救済と再発防止の実効性を優先しました。和解では、1作品あたり約3,000ドルの補償が想定され、最大50万作品が対象とされます。広範な著作権者に対して短期間で補償が行き渡るスキームは、判決確定まで争うよりも現実的な利益をもたらすとの判断です。
今後の著作権侵害裁判に与える影響 — AI時代の新たな地平
他社(OpenAI・Meta・Google)にも波及するか?
今回の和解は、他のAI企業にも大きな波紋を広げています。現在、OpenAIやMeta、Googleも同様の訴訟に直面していますが、「フェアユースでは逃れられない」という前例ができたことで、各社は学習データの合法性をより厳格に管理せざるを得なくなりました。
今後は、「どんなデータを学習に使ったのか」を公表しなければ信頼されない時代が到来するといえるでしょう。
著作権者側の行動にも変化が
著作権者もまた、新たな行動を取り始めています。まず、自らの作品がAIに利用されたかどうかを検出するツール開発が進んでいます。
さらに、出版社がAIライセンス契約を導入し始めました。
米・ジョンズ・ホプキンス大学出版局は著作物の学習利用にライセンス契約を設ける方針を打ち出し、英・Bloomsbury社は著者に同意を求めた上でAI利用を認める仕組みを整備しました。HarperCollins社は作品ごとに学習ライセンス料を設定するなど、具体的なスキームが登場しています。
加えて、英国のPLSや米国のCCCが進める包括ライセンス方式は、将来的に「AI学習用著作物市場」を制度的に形成する可能性を示しています。
こうした流れは、AI開発に対して「利用するなら正規ライセンスを」という強いメッセージとなり、業界全体のルール形成に大きな影響を与えています。
また、複数出版社を束ねて権利処理する包括ライセンス方式の検討も進行中です。これらは単なる個別対応に留まらず、将来的に「AI学習用著作物マーケット」が形成される可能性を示しています。結果として、AI企業は「必要な著作物を正規にまとめて調達する」ことが現実的な選択肢になりつつあります。
日本への影響 — 私たちの創作活動とどう向き合うか?
今回の和解はアメリカで起きた出来事ですが、日本の著作権制度や実務にとっても無関係ではありません。むしろ、近い将来、同様の問題が日本でも顕在化する可能性は十分にあります。
日本の著作権法では、第30条の4から第47条の8にかけて、AI学習や情報解析に関わる規定が整備されています。これらの条文は、研究開発や機械学習のために著作物を複製・利用することを一定範囲で認めており、著作権者の事前許諾を不要とする場合があります。これは、AIやビッグデータの発展を阻害しないようにするための制度的配慮といえるでしょう。
特に関連する条文は以下のとおりです:
第30条の4:著作物を情報解析のために利用できることを定める基本規定。テキストマイニングやAI学習の根拠条文。
第47条の5:コンピュータによる情報解析のための利用を認める規定。機械学習を含み、著作権者の許諾は不要。ただし「著作権者の利益を不当に害しない」ことが条件。
第47条の6:コンピュータに著作物を記録・保存することを認める規定。
第47条の7:コンピュータ処理の過程で必要な一時的複製を認める規定。
第47条の8:ネットワークを通じた送信過程で必要となる一時的複製を認める規定。
ただし、これらの条文には共通して**「著作権者の利益を不当に害しない範囲」**という大前提があります。つまり、学習目的での利用自体は許されても、その結果生じるアウトプットが元の著作物に依拠していたり、著作権者の収益機会を奪ったりするような場合には、侵害と判断される余地が残されています。
例えば、商用AIが小説家やイラストレーターの作品を無断で学習し、酷似した文体や絵柄を再現した生成物を大量に生み出すとどうなるでしょうか。利用者が本来購入するはずだった作品を代替する形になれば、著作権者の経済的利益は明らかに損なわれます。この場合、「情報解析だから合法」という単純な理屈は通用せず、むしろ侵害の認定に向かう可能性が高いと考えられます。
さらに、日本でも「自分の作品を学習データに使われたくない」というクリエイターの声が今後高まることは避けられません。その場合、AI企業に対して「どんなデータを学習に用いたのか」を開示させる透明性確保や、利用制限をルール化する制度的議論が進むでしょう。実際、欧州ではすでにAI学習に関する透明性義務を法制化する動きがあり、日本も無関心ではいられない状況です。
言い換えれば、現在「研究開発を支える柔軟な規定」として位置づけられている第30条の4から第47条の8の諸条文は、今後の運用次第で「権利者を保護する規制」として機能する方向にシフトしていく可能性があります。こうした変化を見越し、個々のクリエイターや中小事業者も早い段階から備えを進めておくことが、実務上ますます重要になるといえるでしょう。
中小クリエイター・個人事業者はどう対応すべき?
ここまでの話を「大企業と大作家の特別な事例」と感じる方もいるかもしれません。ですが、実際には中小クリエイターや個人事業者にとっても無関係ではありません。なぜなら、ブログ記事、イラスト、写真、音楽、講演資料──これら日常的に公開される創作物も、AIの学習対象になり得るからです。
そのため、まず大切なのは**「自分の作品が無断学習に使われないよう、意思を明示すること」**です。たとえば、サイトや配布物に「この作品をAI学習に使用することを禁じます」と明記するだけでも、後のトラブル防止につながります。また、Creative Commonsライセンスなどを活用し、「AI利用は不可」など条件を付す方法もあります。
次に重要なのは、契約の場面での備えです。クライアントや業務委託先と契約を結ぶ際に、「納品物をAI学習に利用することはできない」といった条項を入れておくことが、後々の紛争を防ぐ有効な手段になります。
さらに、将来的には「自作がAIに使われたかをチェックする仕組み」も中小クリエイターにとって重要になっていきます。こうしたツールが普及すれば、自分の作品が無断学習されていないかを定期的に確認できるようになるでしょう。
行政書士としては、このような「デジタル著作権の管理」に関して、契約書作成やライセンス設計、初期対応のアドバイスなどを通じて、クリエイターや小規模事業者を支援できると考えています。つまり今回の和解は、「大企業の問題」ではなく、あらゆるクリエイターが考えるべき課題を突きつけた出来事なのです。
まとめと行動喚起
今回のAnthropicによる巨額和解は、単なるアメリカのニュースではなく、私たち一人ひとりの創作活動やビジネスにも深い示唆を与える出来事でした。AIの進化を止めることはできませんが、「どのように共存するか」を考えることは、今からでも始められます。
行政書士は、法務・契約・手続・制度活用の幅広さで勝負できる専門家です。補助金、著作権契約、家族信託、遺言、相続──これらを「実際に中小事業者や個人が使える形」に落とし込むことができます。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
行政書士だからこそできる視点で、皆さまの創作と事業をサポートします。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚著作権シリーズはこちらから
・第1回:「著作権の実名登録と第一発行年月日登録って何?」初心者にもわかりやすく解説します!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
・第4回:これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話
・第5回:ネットにあるもの、勝手に使ってもいいの?~画像・文章・音楽などの取り扱い注意ポイント~
・第6回:自分の作品が勝手に使われた!そんなときどうすれば?
・第7回:お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶