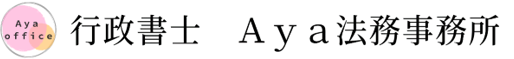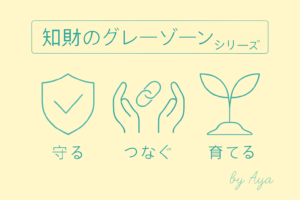こんにちは! 行政書士Aya法務事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの“知的財産(知財)”に関するお悩みをサポートしています。
最近、ブログやSNS、YouTubeなどを使って自分の作品やコンテンツを発信する方が急増しています。発信の手軽さが増す一方で、「著作権って実はよくわかっていない」「気づかないうちに誰かの権利を侵害してしまっているかも…」といった不安の声も多く寄せられています。
特に小規模事業者の方にとっては、「専門的な法律の知識がない」「社内に法務担当がいない」というケースも多く、うっかりのミスが大きなトラブルにつながることも少なくありません。
このブログでは、著作権のルールやリスクを、「こわいもの」としてではなく、“味方”にするための基本知識として、できるだけわかりやすくお伝えしています。
今回は、著作権シリーズの締めくくりとして、今日からすぐに意識できる「著作権の心得10か条」をご紹介します。 難しい法律用語はできるだけ使わず、事例とともに実務のヒントをまとめていますので、ぜひ最後までお読みいただき、ご自身の活動に役立てていただけたら嬉しいです。
目次
- ① ネット上の情報は“自由”ではない
- ② 引用と転載の違いを知る
- ③ フリー素材の条件を確認する
- ④ 意外なところに他人の権利が
- ⑤ 著作権表示がなくても権利はある
- ⑥ 出所不明の素材は避ける勇気を
- ⑦ AI生成物にも注意が必要
- ⑧ 自分が著作権者になることも
- ⑨ 他人に使わせるときは条件明示を
- ⑩ 迷ったら「避ける」か「確認」
- 🧭 まとめ
① ネット上の情報は“自由”ではない
インターネットには、写真・音楽・文章・動画など、さまざまなコンテンツがあふれています。SNSの投稿、ブログの本文、画像検索でヒットするイラストやロゴ、さらにはAIが生成したコンテンツまで、一見“誰でも自由に使ってよさそう”な雰囲気を感じる方も多いかもしれません。
しかし、それらは基本的にすべて「著作物」であり、著作権によって保護されています。 たとえ無料で公開されていても、たとえ「ネットで簡単に見つけられた」としても、それを“勝手に使ってよい”ということにはなりません。
🧾事例
ある飲食店が、インターネット上で見つけた可愛らしいキャラクターのイラストを、自店のチラシに無断で使用しました。 見た人がSNSで拡散した結果、原作者の目に留まり、著作権侵害として損害賠償を求められたのです。
このように、「ネットで拾った画像だから大丈夫」と軽く考えていたことが、思わぬ法的リスクに発展する可能性があります。
✅ポイント
- 「誰でも見られる」と「誰でも使ってよい」はまったく違います
- 著作物を使いたい場合は、利用条件を確認し、必要に応じて許諾を得ましょう
- 自分で撮った写真や、自分で描いたイラストを使うのが安全です
② 引用と転載の違いを知る
著作物をブログやSNSなどに掲載する際、「引用だから大丈夫」と思ってしまいがちですが、「引用」と「転載」には明確な違いがあります。
📘引用とは?
- 他人の著作物を、自分の著作物の中で“必要な範囲だけ”取り入れること
- 出典を明示すること
- あくまで「自分の文章が主」「引用は従」の関係であること
このようなルールを守っていれば、著作権者の許可を得なくても「引用」として認められる可能性があります。
📕転載とは?
- 他人の文章や画像などを、そのまま“そっくり掲載”する行為
- 引用のような限定ルールに基づいていない場合、原則として著作権者の許可が必要です
🧾事例
とあるブログ運営者が、新聞社の記事をそのまま全文コピーして掲載したところ、「引用のつもりだった」と主張したものの、実際は転載に該当すると判断され、新聞社から法的措置の警告を受けました。
✅ポイント
- 「引用」はルールを守ればOK、「転載」は基本的にNGと考えておきましょう
- 自分の意見や解説と組み合わせた場合にだけ、「引用」の可能性が出てきます
- ニュースサイトなどからの転載は特にリスクが高いため注意が必要です
③ フリー素材の条件を確認する
「フリー素材」という言葉はよく耳にしますが、実際には“自由に何でもできる素材”ではありません。サイトごと・素材ごとに利用条件が細かく定められていることが多く、条件を無視して使用すると著作権侵害とみなされることもあります。
具体的には、以下のような条件が設定されている場合があります:- 商用利用:許可/禁止
- クレジット表記:必須/任意
- 改変・加工:可/不可
- 再配布・二次利用:可/不可
🧾事例
ある動画クリエイターが、フリー素材サイトでダウンロードしたBGMを商用動画に使用したところ、その素材には「クレジット必須」という条件があったため、クレジット表記を省略して公開してしまい、配信停止を求められたケースがあります。
✅ ポイント
素材サイトのライセンス条項を必ず確認すること。「無料」「フリー」という文言だけで安心せず、不明点があれば提供元に問い合わせを。
④ 意外なところに他人の権利が
テンプレート・フォント・アイコン・背景素材など、目に見える“素材”であっても、他人の著作権がかかっているケースがあります。特に商用利用時は、こうした“パーツ素材”の権利を軽視してはいけません。
🧾事例
起業家が無料テンプレートを使ってチラシを作成したところ、そのテンプレートに含まれていたフォントが“商用不可ライセンス”だったため、著作権者から使用停止と切り替えを求められたケースがあります。
✅ ポイント
パーツ素材も著作物とみなす。フォントやアイコンのライセンスを確認し、自作素材を中心に使うのが最も安心です。
⑤ 著作権表示がなくても権利はある
著作権は、創作した時点で自動的に発生します。つまり、作品に「©」マークが付いていなくても、著作物として保護されています。
「表示がない=自由に使ってもよい」と勘違いされがちですが、これは誤った理解です。©マークはあくまで著作権者を示す表示であって、権利の発生とは無関係です。
©マーク補足:
・意味:copyrightの略で、所有者の権利主張の意を表す
・例:© 2025 Aya Office/© 山田太郎
・法的効果:表示の有無にかかわらず、著作権は成立
🧾事例
著作権表示のない記事を無断転載したところ、著作者側から侵害として訴えられたケースがあります。「表示がないから自由に使える」との主張は認められませんでした。
✅ ポイント
表示の有無ではなく、出所と利用条件を確認。自分の作品には©マークをつけて権利を明示しておくと安心です。
⑥ 出所不明の素材は避ける勇気を
Pinterest やまとめサイト、SNS転載画像など、出所が不明な素材の使用には常にリスクが伴います。著作権者が特定できなければ、許可を取ることができません。
🧾事例
ある企業がSNSで見つけた風景写真を広告に使ったところ、撮影者から著作権侵害で訴えられ、賠償金と回収対応を余儀なくされた例があります。
✅ ポイント
出所が不明な素材は避けるのが安全。信頼できる素材サイトや契約可能な素材を優先しましょう。
📌 Pinterest利用時の注意点
Pinterest(ピンタレスト)は、ユーザーが気に入った画像を“ピン”して収集・共有するプラットフォームですが、掲載されている画像の多くは他のWebサイトから転載されたものです。
そのため、Pinterest上にある画像は「自由に使っていい素材」ではありません。たとえ「保存」「共有」ボタンがついていても、それはPinterest内での利用を前提としているため、商用利用や自分のブログ・チラシなどに転載することは基本的にNGです。
特に気をつけたい点:
- 画像の出所が不明である(オリジナル作者がわからない)
- リンク先のサイトでも利用条件が明記されていない場合が多い
- 「まとめサイト経由」などで正確な著作権者にたどり着けないケースがある
Pinterestの「ピン」はあくまで“リンク”や“メモ”であり、著作物の使用許諾とは関係ありません。
✅ ポイント:
Pinterestの画像を使用する際は、必ず元サイト・元著作者のライセンスを確認し、必要であれば許可を取りましょう。
安心して使える画像が必要な場合は、著作権表示や利用規約が明確なフリー素材サイトを利用するのが賢明です。
⑦ AI生成物にも注意が必要
AI生成された画像や文章は、一見「オリジナル」に見えますが、学習データに著作物が含まれているケースがあるため、著作権問題の可能性があります。
🧾事例
AIで生成したイラストを広告に使ったところ、有名キャラクターと酷似していたため権利元から差し替えを要求された例があります。
✅ ポイント
AI生成物も“無制限に使える”わけではありません。利用規約・著作権・商標・肖像権を確認し、必要なら専門家に相談を。
⑧ 自分が著作権者になることも
書いた文章、撮った写真、作図したイラスト…創作性があれば、それ自体が著作物です。つまり、あなたも著作権者になり得るということです。
🧾事例
個人が投稿した写真が無断で商用に使われ、著作者が権利を主張して謝罪と賠償を得た例があります。
✅ ポイント
自分の作品には © 表示をつけ、利用条件を明示しておくと無断使用を防ぎやすくなります。
⑨ 他人に使わせるときは条件明示を
自分の作品を他人に使ってもらう際、条件を明示しておかないと誤解やトラブルにつながります。
記載すべき条件の例:
- 商用利用 可/不可
- クレジット表示 要/不要
- 改変 可/不可
- 再配布・二次使用 可/不可
- 利用期間・地域制限
🧾事例
ある素材提供者が「自由に使って」と表明した素材が営利利用され、後にトラブルになったことがあります。
✅ ポイント
利用許諾を出す場合は、契約書・メール等で条件を明文化し、範囲を限定することが大切です。
⑩ 迷ったら「避ける」か「確認」
著作権に関して判断に迷ったら、無理をして使わず、「使わない」か「確認を取る」対応が最も安全な選択肢です。
🧾事例
卒業制作で人気曲をBGMに使い、公開後に権利元から削除要求を受け、上映を差し止められた例があります。
✅ ポイント
迷ったときは立ち止まり、使用許可を取るか代替素材を使うか、必要なら専門家に相談してください。
🧭 まとめ
著作権トラブルは、難しい知識よりも「軽く扱わない意識」が大切です。「気づかず使ってしまう」「なんとなく大丈夫だろう」と思ってしまうことが最大のリスクです。
想像力を持つこと:「もしこれが自分の作品だったら?」と考える。
情報を確認すること:素材の出所やライセンスを必ずチェック。
行動すること:迷ったら使わず確認し、許諾を得るか別素材を使う。
記録を残すこと:許可書・契約書・利用条件は重要な証拠。
著作権を“守ること”は、自分の信頼と作品の価値を守ることでもあります。「知らなかった」で済まされない時代だからこそ、「正しく知って、賢く使う」意識を大切にしていきましょう。
知財をもっと身近に。もっと味方に。 \お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚 過去記事はこちら
・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
・第4回:これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話
・第5回:知らなかったでは済まない!著作権トラブルを防ぐ3つの鉄則
・第6回:自分の作品が勝手に使われた!そんなときどうすれば?
・第7回:お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話
・第8回:著作権フリー?パブリックドメイン? よく聞く言葉をやさしく解説
・第9回:著作隣接権ってなに?画像・音楽・演奏…使う前に知っておきたい注意点