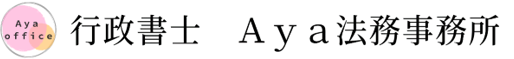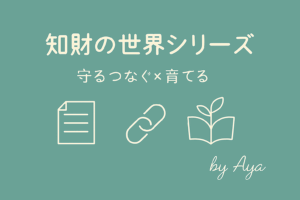著作権シリーズ第7回 お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。
私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
今回は、「お客さんとやりとりするときに気をつけたい、著作権と契約の話」について、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。
お仕事で発生する「著作権」、誰のもの?
たとえば外部のデザイナーさんにロゴやチラシを作ってもらったとき。
そのデザインの「著作権」は、基本的には制作者=著作者にあります。
「お金を払ったから、自分のもの」ではない点に注意が必要です。
- 印刷して配布していいか
- WebやSNSに掲載していいか
- 別のデザイナーに加工してもらってよいか
こうした使用範囲は、契約で事前に取り決めておく必要があります。
著作権の「譲渡」と「利用許諾」の違い
| 用語 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 著作権譲渡 | 著作権そのものを相手に渡す | 著作権ごと買い取って自由に使う |
| 利用許諾 | 決められた範囲で使わせてもらう | 印刷のみOK、SNSはNG など条件つき |
「自由に使いたい」なら、著作権の譲渡または広い範囲の利用許諾が必要です。
よくあるトラブルと予防のポイント
● トラブル例1:
「前に作ってもらったチラシを他のイベントでも使ったら、著作権侵害と指摘された」
→ 契約に「利用目的・範囲」が明記されていなかったため、制作者側が“無断使用”と判断。
● トラブル例2:
「納品されたデザインを別の業者に加工してもらったら、クレームが来た」
→ 改変権(著作者人格権)に抵触する可能性あり。
どちらも、契約で事前に内容を明文化しておくことで防げたトラブルです。
契約書や合意書で押さえたいポイント
- 著作権の扱い:譲渡か、利用許諾か
- 利用できる範囲:印刷・WEB・SNS・媒体の限定
- 使用期限・地域・金額
- 著作表示:クレジット表記の要否
- 修正回数・納品形式など
理想は書面での契約書ですが、メールやチャットでも内容を残すことが大切です。
契約書のテンプレートや相談先
- 文化庁やクリエイター団体が、著作権契約の参考資料を公開しています
- フリーランス同士や個人間でも、簡易的なひな形を使うと安心です
- 不安がある場合は、専門家(弁護士や行政書士など)に相談を
まとめ
- 著作権は、依頼した側ではなく「作った人」に帰属するのが原則
- 譲渡と利用許諾の違いを理解することで、安心して使える
- 契約内容は、必ず書面や記録に残しておこう
■ 最後に
著作権を意識することは、他人の創作を大切にすること。
そしてそれは、自分自身のアイデアや作品を守ることにもつながります。
著作権の話は、すぐに答えが出ないことも多いですが、私自身も日々学びながら、こうして少しずつ伝えていけたらと思っています。
どのくらいの方に届いているかは分かりませんが、「あ、役に立ったな」と思ってもらえることを願って、これからも続けていきます。
また気が向いたときに、のぞいていただけたらうれしいです。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちらから
・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
・第4回:これ、使っていいのかな?――著作者がわからない作品と著作権の話
・第5回:知らなかったでは済まない!著作権トラブルを防ぐ3つの鉄則
・第6回:自分の作品が勝手に使われた!そんなときどうすれば?
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日
お知らせ2025年12月31日2025年大晦日