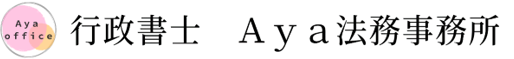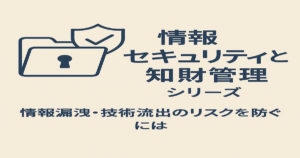食の安心×知財シリーズ第8回:食料システム法とは?
――農場から食卓までをつなぐ新しいルール
目次
- 1. はじめに
- 2. なぜ今、食料システム法なのか
- 3. 法律の目的と位置づけ
- 4. 法律の仕組み(2つの柱)
- 5. HACCP・GAP・IPMとのつながり
- 6. 導入事例(物流・製造)
- 7. 補助金・支援制度の活用(計画認定制度と連動)
- 8. 知財・知的資産の観点
- 9. おわりに
1. はじめに
こんにちは!これまでのシリーズで、HACCP(食品衛生管理)、GAP(農業生産のルール)、IPM(病害虫管理)を解説してきました。いよいよ完結編として、2025年10月に施行される「食料システム法」を取り上げます。食の安全・安心を超えて、持続可能な食料供給という未来へ向かう“新しい枠組み”を、実務目線でやさしく解説します。
2. なぜ今、食料システム法なのか
食料安全保障の観点では、日本の食料自給率がカロリーベースで伸び悩む中、海外要因(紛争・気候・為替)による価格高騰が家計と事業者を直撃しました。将来も地政学リスクと気候リスクは続くため、「安定供給の仕組み」を法制度として整える必要があります。
環境問題では、食品ロス(年間数百万トン規模)や輸送・加工に伴うエネルギー使用が課題。脱炭素・省エネ・資源循環の流れに沿い、食品産業にも構造的な改善が求められます。
産業構造の面では、食品産業の大半を占める中小企業が人手不足・低収益に悩み、価格転嫁の難しさから投資に踏み切れない実情があります。産業全体の底上げには、国の後押しと公正な取引環境が不可欠です。
3. 法律の目的と位置づけ
正式名称は「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び取引の適正化に関する法律」。長い名称に、目的がすべて詰まっています。
- 食品の持続的な供給(食料安全保障)
- 事業活動の促進(環境負荷の低減、物流効率化、地域連携)
- 取引の適正化(公正な価格交渉、商慣習の是正)
- 消費者利益の増進(選べる情報の提供、透明性)
生産・加工・流通・小売・外食・消費の全工程を横断し、フードチェーン全体で持続可能性と安心を底上げする“統合法”として設計されています。
4. 法律の仕組み(2つの柱)
法律の核は「2つの柱」です。
① 事業活動の促進
- 安定取引の構築:農業者と食品事業者の長期的パートナーシップ、原材料の安定確保
- 物流の合理化:共同配送・デジタル管理に加え、モーダルシフト(トラック輸送を鉄道や船舶に切り替える取り組み)を推進。大量輸送に適した手段へ転換することで、CO₂排出量削減やドライバー不足対策を実現。
- 環境負荷低減:再エネ導入、フードロス削減、資源循環の推進
- 消費者選択支援:環境配慮・生産背景・トレーサビリティの見える化
② 取引の適正化
- 価格交渉の適正化:原材料・物流・エネルギーコストを踏まえた公正な価格設定
- 商慣習の是正:過度な値引き・不合理な短納期等の改善
- 国の関与:実態調査・助言・勧告等により公正な取引環境を整備
これは単なる規制ではなく、食品産業全体を持続可能で透明性の高い仕組みへと進化させるための基盤なのです。
「農場から食卓までの“足跡”を確認できる仕組み」。どの農場・どんな資材で育てられ、どの工場・どのルートを経て店頭に届いたかを記録し、問題発生時の迅速な原因追跡と、消費者の安心につなげます。
5. HACCP・GAP・IPMとのつながり
GAPは安全な原材料の確保、IPMは環境負荷の低い生産、HACCPは加工・流通の衛生管理という役割。食料システム法はこれらの実務を“全体最適”として束ね、フードチェーン全体の信頼と効率を高めます。
6. 導入事例(物流・製造)
🚚 物流・小売業の例
ある物流企業では、高効率機器や太陽光発電を導入し、複数拠点で再エネ電力を使用しています。
さらに、食品廃棄を「見える化」する計量システムを導入。廃棄量の発生場所や要因を把握することで、ロスを減らす改善策を打ち出しました。
加えて、長距離輸送においては「モーダルシフト」に取り組みました。
従来はトラックで行っていた幹線輸送を、鉄道や船舶に切り替えることで、CO₂排出量を大幅に削減。ドライバー不足への対応にもつながりました。
最終的な店舗配送はトラックが担うため効率も損なわれず、環境配慮と効率化を両立した輸送モデルとして評価されています。
🏭 製造業の例
ある食品メーカーは製造過程で発生する端材をパウダー化して新商品に活用。温室効果ガス(GHG)排出量の算定システムも導入し、数値を外部公表しました。ラベルやPOPで「資源循環と脱炭素」のストーリーを伝えた結果、ブランド力と販売が向上。ネーミングやロゴは商標で保護し、算定手法や加工条件は営業秘密として管理しています。
7. 補助金・支援制度の活用(計画認定制度と連動)
食料システム法に基づく「食品産業の発展に向けた計画認定制度」の認定を受けると、次のような支援が受けられます。
- 金融支援:民間金融機関からの資金調達に際し、食品等持続的供給推進機構の債務保証を利用可能。
- 他法制度との連動:認定計画が産業競争力強化法の事業再編計画、または中小企業等経営強化法の経営力向上計画の要件を満たす場合、長期・低利の大規模融資や中小企業投資育成会社の出資、会社法の特例等の支援が受けられます。
- 補助金適正化法の特例(手続簡素化):本来は補助金交付財産の目的外利用に省庁承認が必要ですが、連携支援計画の認定を受けた場合は承認済みとみなされ、柔軟な活用が可能になります(活用事項の計画記載が必要)。
単発の補助金にとどまらず、認定計画を軸に「融資・出資・法的特例」を組み合わせることで、投資負担を抑えつつ持続的な改善を進められます。
8. 知財・知的資産の観点
- ブランド・認証:商品名やロゴ、認証マークの適正表示は商標権と直結。
- マニュアル/トレーサビリティ:著作権や営業秘密で守れる可能性。
📝 補足:マニュアルやチェックリストは、単なる事実・手順 の羅列では著作権の対象になりません。一方、図表の工夫、文章構成、独自の言い回し、事例の選定・配置など創作性のある表現が含まれる場合は著作物として保護され得ます。
トレーサビリティシステムでも、ソフトウェアの設計書・画面デザイン・報告書の体裁や解説文といった創作的な部分は著作権の対象になり得ます。逆に、仕入日・数量・納入先などの生データ(事実情報)は著作権の対象外ですが、データの整理方法や可視化の工夫に独自性があれば保護の可能性が生まれます。あわせて、ノウハウは秘密保持契約(NDA)や情報管理で守るのが実務的です。
- 共同研究・取引情報:NDAや共同研究契約で権利関係を明確化。
- 企業価値担保権(2026年予定):無形資産を資金調達に活かす選択肢に。
9. おわりに
HACCP・GAP・IPMで築いた実務を土台に、食料システム法は「食の安心と未来」をつなぐ総仕上げです。中小事業者にとっても、制度を味方につければ信頼の獲得と新しい成長のチャンスになります。
\食の安全を未来へつなぐ。知財で事業を守る。お気軽にご相談ください!/
📚過去記事はこちら
▶第1回:O-157がきっかけだった ― HACCPとの出会い!
▶第2回:味だけじゃない“見えない価値”も守る― 小さなお店が知っておきたい知的財産リスクとは?
▶第3回:見た目で選ばれる時代― パッケージ・店舗デザインの“知財リスク”と守り方
▶第4回:HACCPって何?飲食店・製造・卸まで―安心をつくる“衛生管理”の基本
🔗参考リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに?
著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに? 相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは?
相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは? 著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は?
著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は? 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説