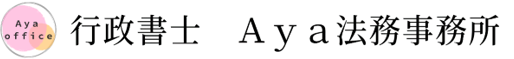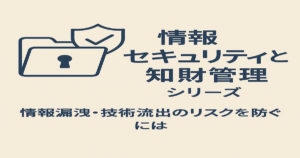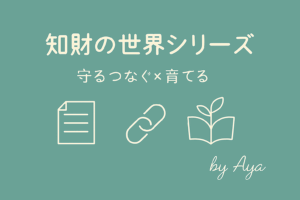著作権シリーズ第3回 個人・小規模事業者のための著作権譲渡契約入門
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
今回は、「著作権譲渡契約」について、よくある失敗例や契約書に入れておくべき重要なポイントをわかりやすくご紹介します。
■ そもそも著作権って誰のもの?
たとえば、あなたが次のような制作物を外注したとします:
- お店のロゴ
- パンフレットのデザイン
- 商品紹介のブログ記事
- 動画編集やナレーションの収録
このような「創作されたもの=著作物」は、基本的に作った人(制作者)に著作権が発生します。つまり、あなたが発注者であっても、自動的にその権利を得るわけではないのです。
■ よくあるトラブル3選(実例)
① ロゴが自由に使えない!
AさんはSNSや広告に使うロゴを外注。納品されたロゴを看板やTシャツに印刷しようとしたところ、「著作権は譲っていません。用途が限られます」とデザイナーに言われてしまいました。
② 記事を勝手に編集できない!?
Bさんはブログ記事をライターに依頼。納品後、内容を一部修正しようとしたら「著作人格権があるので改変しないでください」と指摘されました。
③ イラストの利用範囲でモメた…
Cさんはチラシ用にイラストを発注しましたが、「Web広告にも使いたい」と伝えたところ、「契約にない用途には使えません」と拒否されてしまいました。
■ 著作権譲渡契約でトラブルを防ごう!
こういったトラブルを防ぐには、制作を依頼する際に契約書を交わすことがとても大切です。
特に次の3つのポイントを押さえておきましょう。
✅ 1. 著作権の譲渡を明記する
「著作物の著作権を発注者に譲渡する」と、明確に書くことが重要です。
これにより、発注者が自由に利用できるようになります。
✅ 2. 翻案権・翻訳権も譲渡対象に
日本の著作権法では、「翻案(=改変)や翻訳などの権利」は特に重要視されており、明記しないと譲渡されたことになりません。
たとえば:
- ロゴの色を変える
- 記事の内容を調整する
- イラストを加工して別の媒体に載せる
こうした使い方をするなら、「著作権法第27条・第28条の権利も含めて譲渡する」と書いておくと安心です。
✅ 3. 著作者人格権についての取り扱い
著作権とは別に、著作者には「著作者人格権」という、人格に関わる権利があります。これは譲渡できないため、契約でどう扱うかをきちんと取り決めておく必要があります。
■ 著作者人格権とは?
主に以下の3つがあります:
- 氏名表示権:名前を表示するかしないかを決める権利
- 同一性保持権:作品を勝手に変えられない権利
- 公表権:いつ、どのように作品を公開するかを決める権利
これらが発注者の利用の妨げになることもあるため、契約では次のようなバランスをとる表現が有効です。
■ 契約例文(著作者人格権の扱い)
著作者は、発注者が本著作物を事業遂行上合理的な範囲で改変・編集・利用する場合においては、著作者人格権を行使しないものとする。
発注者は、著作者の名誉・声望を毀損しないように本著作物を利用するものとする。
このように記載することで、発注者は自由に作品を活用しやすくなり、著作者側も必要な保護を受けられます。
■ まとめ:お互いの安心のために
著作物を外注する際、「納品されたからもう自由に使える」というのは誤解です。
しっかり契約で取り決めておかないと、後々トラブルになる可能性があります。
- 著作権は譲渡されない限り制作者にある
- 27条・28条の権利も対象に含める
- 著作者人格権には配慮しながら、行使しない合意をとる
この3つを押さえておけば、安心して制作物を使い、ビジネスに活かすことができます。
私もまだ勉強中ではありますが、「知らなかった」で困る方を一人でも減らせるよう、これからも知財の情報をわかりやすく発信していきます。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちらから
・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
・第2回:「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに?
著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに? 相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|所有不動産記録証明制度とは?
相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|所有不動産記録証明制度とは? 著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は?
著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は? 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説