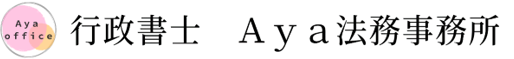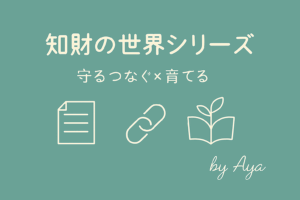著作権シリーズ第2回 「プログラム著作物の著作権管理と創作日の登録が重要な理由」
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
今回は、「プログラム著作物に関する登録」について、具体例を交えてわかりやすくご紹介します。
ソフトウェアやホームページを開発・制作するとき、「著作権」について深く考える機会はあまり多くないかもしれません。
実際、「納品されたからもう自分のもの」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、あとから「著作権は制作者にある」と言われたり、「他社でも同じシステムが使われている」と知ったりして、困ってしまうケースも少なくありません。
特にプログラムなどの無形の成果物は、「誰が作ったのか」「いつ作ったのか」といった情報が曖昧になりがちです。
この記事では、プログラム著作物に関わる著作権の基本と、創作日を証明する方法や著作権譲渡のポイントについて、実務に役立つ形でわかりやすく解説していきます。
プログラムも著作物として守られています
プログラムやソフトウェアと聞くと、技術的で法律とは縁遠いように感じるかもしれません。
でも実は、プログラムも「著作権法」でしっかり守られている作品のひとつです。
例えば以下のようなものは、すべて著作物として扱われる可能性があります:
- ソースコード(Python、JavaScript、HTMLなど)
- 画面のデザインや構成(オリジナリティがある場合)
- 操作マニュアルや仕様書
つまり、プログラムや設計に「創作性」があれば、それだけで法律による保護対象になるんです。
しかも登録などの手続きは不要で、作った時点で自動的に著作権が発生します。
「登録」が必要なのは、後から証明するのが難しいから
「え、じゃあ何も手続きしなくても大丈夫なの?」と思うかもしれません。
確かに、著作権は自動的に発生します。ですが――
実際のトラブルでは、「誰がいつ作ったか」を証明できないことが問題になります。
たとえば、自分が作ったプログラムを別の人が使っていたとき、
「それは自分が先に作った」と主張しても、証拠がなければ説得力がありません。
そんなときに役に立つのが、「創作年月日」をきちんと登録しておくことです。
これによって、いつ・誰が作ったかという“記録”を公的に残しておくことができます。
プログラムの著作権登録はどこでできるの?
実は、プログラム著作物の登録は、文化庁の制度ですが、
申請の受付や実務は「一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)」が一括して担当しています。
プログラム著作権は創作から6か月以内に登録しなければなりません。
6か月を過ぎた場合について
「創作してから6ヶ月を過ぎてしまった場合には、プログラムを登録することはできません。将来、そのプログラムをバージョンアップしてから6ヶ月以内に、創作年月日の登録を申請することをお薦めします。
注:そのプログラムを発行(公表)をしていれば、第一発行(公表)年月日の登録が申請できます。」
出典:SOFTIC よくある質問
登録できる内容には以下のようなものがあります:
- 創作年月日(作った日)
- 誰が著作権者か
- 著作権の譲渡や移転があったか
- 公表された日 など
この登録をしておくことで、もしも後から紛争やトラブルになったときに、「この人がこの日に作った」という事実を公的に証明する材料として活用できます。
ホームページ制作やシステム開発でも、注意が必要です
最近では、ソフトウェアだけでなく、ホームページや業務システムの制作にも著作権の問題が関わってきます。
たとえば、こんな誤解がよくあります:
「ホームページを発注して、納品されたんだから、著作権も自動的に自分のものになってるはず」
でも実はこれ、契約で明確にしていなければ、著作権は制作会社(または制作者)に残っているのが原則です。
以下のようなものも、すべて著作物の対象になります:
- ソースコード(HTML/CSSなど)
- 画像・バナー
- 写真・動画素材
- 文章・キャッチコピー
これらの著作権がどこにあるのかをハッキリさせておかないと、後から修正・再利用したり、他社に制作を引き継いだりするときに問題になることがあります。
著作権譲渡の契約をきちんと交わしておく
こうしたトラブルを防ぐには、契約書で著作権の譲渡や使用条件をしっかり取り決めておくことがとても大切です。
たとえば、次のような条文を契約書に入れておくと安心です:
「本契約に基づき作成された全ての著作物についての著作権は、発注者に譲渡されるものとする」
このように明記することで、「納品物=自由に使っていいもの」になることを法律上もはっきりさせられます。
さらに重要なのは、「何が納品物なのか」も明文化しておくこと。
ソースコード、画像、デザインファイル、テキスト…など、すべて含まれているかどうかも契約で明示しておきましょう。
※著作権法第27条(翻案権)・第28条(翻訳権等)の利用許諾の留保、著作者人格権の取扱いについても明記しておくことはとても大切です。
著作権の管理は、“守る”だけでなく“育てる”ことにもつながります
著作権をきちんと管理することで得られるのは、トラブルの回避だけではありません。
- 自社開発のシステムやツールを資産として評価できる
- クライアントやパートナーとの信頼関係が深まる
- 事業売却やライセンス展開など、ビジネスの広がりに使える
つまり、著作権を「守る」だけでなく、「活かす」「育てる」ことができるのです。
今すぐできる3つの著作権リスク対策
最後に、すぐに始められる著作権対策を3つご紹介します:
1. 創作したプログラムは、SOFTICを通じて登録する
プログラムの著作権を証明するためには「創作日の客観的証明」が重要です。日本では文化庁が運営する「SOFTIC(ソフティック)」という著作権登録制度があります。ここでプログラムのソースコードや完成日時を登録すると、公的な証明書を取得でき、権利保護に役立ちます。
事例
個人のソフトウェア開発者Aさんは、自作のスマホアプリをSOFTICに登録しました。後に他者が似たアプリを公開した際、AさんはSOFTICの登録証明を提示し、「自分が先に開発した」ことを法的に証明できたため、トラブルを未然に防げました。
ポイント
- SOFTIC登録は任意ですが、権利を守る強力な証拠になります。
- ソースコードの一部でも登録可能で、登録費用も比較的リーズナブルです。
2. 著作権譲渡や使用範囲を契約書に明記する
ソフトウェア開発においては、開発者と発注者の間で著作権の譲渡や使用範囲を明確にしておくことが非常に重要です。口頭や曖昧な合意は後のトラブルの原因となります。
事例
小規模事業者B社は、フリーランスのプログラマーにシステム開発を依頼。しかし契約書で著作権譲渡が明記されておらず、完成後にプログラマー側がソースコードの使用権を制限したため、B社は二次利用や改変ができず困りました。
ポイント
- 契約書に「著作権の譲渡有無」「使用範囲(独占的・非独占的)」「改変の可否」などを明記する。
- 譲渡しない場合でも、使用権(ライセンス)の範囲を具体的に決める。
- 納品後の権利関係をトラブルなく明確にすることで、安心して運用できる。
3. 制作・開発の際は、納品物とその権利関係を事前に確認する
制作物の納品時に、ソフトウェアの内容だけでなく、権利関係の確認も必ず行いましょう。仕様書や契約書と納品物が一致しているか、権利が問題なく移転されているかをチェックします。
事例
個人開発者Cさんは、クライアント向けにWebシステムを開発し納品。しかし納品後、クライアントが「権利譲渡されていない」と主張。Cさんは納品時の契約書と納品物の一覧を提示し、納品物の範囲と権利譲渡が明確であることを示して解決しました。
ポイント
- 納品物リスト(ソースコード、ドキュメント、バージョンなど)を作成・保存する。
- 契約書と照らし合わせて、納品物と権利の範囲が合致しているか確認。
- 納品時に「受領確認書」や「権利譲渡確認書」を交わすのが理想。
まとめ:創作と同時に「証明」も備えましょう
プログラムやWeb制作は、目に見えにくい知的な財産です。
だからこそ、「作った」という事実と、「どう使えるか」というルールをしっかり残しておくことが、ビジネスの安心につながります。
著作権は「守ってくれる法律」でもありますが、
自分から“守りに行く”ための備えが、今の時代にはとても大切です。
私もまだ勉強中ではありますが、「知らなかった」で困る方を一人でも減らせるよう、これからも知財の情報をわかりやすく発信していきます。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちらから
・第1回:著作権の実名登録とは?第一発行年月日との違いも初心者向けに解説!
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。