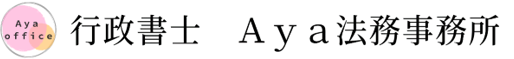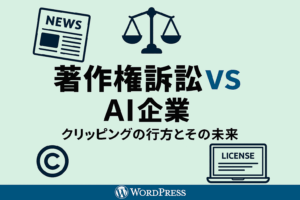情報セキュリティと知財管理シリーズ第3回:裁判で「営業秘密と認められなかった」
――【コラム①】実例に学ぶ!契約や制度だけでは守れない理由
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。
私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
営業秘密を守っていたつもりが、裁判で「営業秘密ではない」と判断された――。そんな事例は、実は珍しくありません。もしかしたら、あなたの会社や事務所でも同じことが起きるかもしれません。
今回は、ある製造業の事例を通して、契約や制度だけでは守れない“営業秘密”の現実と、その対策についてお話しします。
ある製造業の裁判事例から
◆ 事件のあらまし(ストーリー調)
10年かけて開発した製品の製造マニュアル。社長は「これは会社の命綱だ」と思い、外部に出さないよう社員にも口酸っぱく言っていました。
ところがある日、退職した技術者が似たような製品を別会社で製造していることが発覚。「秘密保持契約(NDA)も結んでいたのに…これは完全に営業秘密の侵害だ!」と訴えました。
◆ 裁判所の判断
裁判所は、残念ながらこのマニュアルを「営業秘密」とは認めませんでした。理由は以下の通りです。
- 書類に「機密」表示がなかった
- 社内サーバーで誰でも閲覧できる状態だった
- 一部内容が展示会資料やウェブで公開されていた
他人事ではない3つの落とし穴
1. 秘密管理性の不足
「社内の誰でもアクセスできる状態」は、秘密管理していないと見なされやすい。
2. 非公知性の欠如
一部でも公表されていると、全体が保護されない場合がある。
3. 価値の立証不足
「有用性」を証明できなければ、保護対象とされない。
NDAや制度だけでは守れない理由
- NDAはあくまで契約。裁判では「日常的な管理実態」が重視されます。
- 形式的な契約や注意喚起では不十分です。
- 「守る体制を整えている証拠」がなければ、法律の盾にはなりません。
今日からできる営業秘密管理のチェックリスト
- 秘密情報に明確なラベル・表示をつけているか
- アクセス権限は業務上必要な人に限定しているか
- 閲覧・持ち出し履歴を記録しているか
- 退職・転職時に返却・削除確認をしているか
- 公表資料と非公表資料を明確に区分しているか
まとめ ― 守るのは制度ではなく日常の運用
この事例、もしかするとあなたの会社や事務所にも当てはまる部分があるのではないでしょうか。NDAは大切ですが、それだけでは不十分。日々の運用こそが、営業秘密を守る本当の力になります。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちら
・第1回:技術流出で書類送検!営業秘密の持ち出し事件から学ぶ、企業が取るべき情報管理対策とは?
・第2回:NDA(秘密保持契約)で本当に情報は守れる?基本条項と見落としがちな落とし穴を解説!
🔗関連リンク(外部サイト)
✅ 中小企業庁:知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日
お知らせ2025年12月31日2025年大晦日