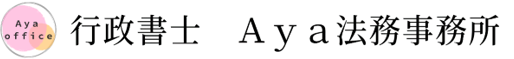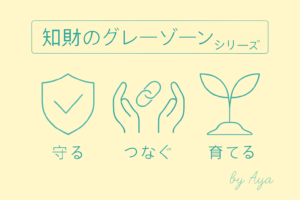知財のグレーゾーンシリーズ第3回:知財と契約書― NDA・ライセンス・共同開発の基礎
こんにちは!
知財のグレーゾーンシリーズも第3回目となりました。
今回は「知財と契約書」についてです。
「契約で押さえておくべき視点」や「書かないことで起こるトラブル」など、身近な事例を交えてお伝えします。
なぜ契約書が重要なのか?
技術やアイデアは「形がない」だけに、
誰が使えて、どう使ってよいかをはっきりさせないと、あとで揉める原因に。
契約書は、その「ルール」を書き留める大切なツールです。
📌 たとえば…
あるベンチャー企業が発明した新素材を、取引先に見せたところ、
試作品がSNSに無断で掲載され、他社に模倣された…
→ 実は「NDAを結んでいなかった」ことが原因でした。
契約で押さえておくべき5つの視点
中小企業庁の知財取引ガイドラインでも強調されているのが、以下のような点です:
- 目的の明確化:どのような共同作業・技術提供をするのか?
- 秘密情報の範囲:NDAにおいて何を「秘密」と定義するか
- 知的財産の帰属:開発成果の権利をどちらが持つのか?共同か単独か?
- 利用条件の明示:ライセンスの範囲(地域・用途・再利用の可否)など
- 契約終了後の取扱い:資料・秘密情報の返却や削除、再利用の制限など
📌 事例
共同開発したアプリの機能について、契約に「どちらが著作権を持つか」が明記されていなかったため、
公開後に「この機能はうちのアイデアだ」と揉めることに…
秘密保持契約(NDA)の落とし穴
NDAは定型で済ませがちですが、次の点に注意が必要です:
- 目的外使用の禁止:「話さない」だけでなく「使わない」ことも明示する
- 契約終了後の扱い:情報の返還義務、データの削除などを明記
- 第三者への再提供の可否:外注先やグループ会社に勝手に回されないよう対策
📌 よくあるミス
展示会に向けて、外部デザイナーに試作品の写真を見せたら、
デザイナーのポートフォリオに掲載されてしまった。
→ NDAに「目的外使用の禁止」「終了後の情報削除」がなかったため対応が困難に…
ライセンス契約・共同開発契約でよくある曖昧表現
- 「善良な管理者として扱う」「誠意をもって協議」
- 「必要に応じて提供する」などの曖昧な表現は、
トラブル時に法的拘束力が薄く、実効性が担保されません。
📌 注意点
「可能な限り協力する」と書かれていたが、
トラブル発生時に「協力したかどうか」の基準があいまいで話が進まず…
「書かない」ことで起こるトラブル
- 成果物が誰のものか決まっておらず、あとで「うちのアイデアを勝手に使われた」と主張される
- 「口頭で確認した」として、契約と異なる認識を主張される
- 提供した技術が、想定外の形で再利用されてしまう(目的外使用)
📌 実際にあったケース
業務委託契約をした際、成果物の著作権について何も書かれておらず、
後日クライアントが「うちが権利を持っている」として無断で販売開始。
→ 実は委託側が著作権を保持していたため、権利侵害に。
おわりに
契約書は、相手との信頼関係を壊すものではなく、
「信頼を明文化する」ツールです。
私もまだまだ勉強中ではありますが、「知らなかった」で困る方を少しでも減らせるよう、
これからも知財のことを、できるだけわかりやすく発信していきます。
また気が向いたときに、のぞいていただけたら嬉しいです。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚 これまでの記事はこちらから
・第1回 :営業秘密が漏れる典型パターンと防止策を解説!
・コラム①:営業秘密と契約の穴〜守ったつもりが、守れてなかった〜
・第2回 :不正競争防止法の落とし穴~「盗用された!」と思っても守れないこともある?~
・コラム②:SNS時代の知財トラブル ― 不正競争防止とSNSの罠
・コラム③:デジタル社会の影 ― SNS時代に潜む詐欺と誤解
🔗外部リンク
👉中小企業庁:知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日
お知らせ2025年12月31日2025年大晦日