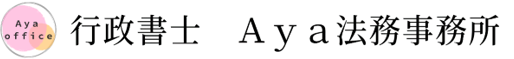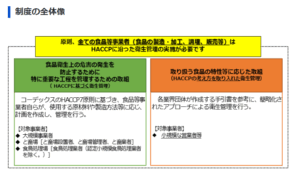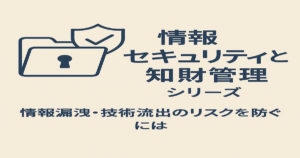🍱食の安心×知財シリーズ第4回:HACCPって何?
飲食店・製造・卸まで―安心をつくる“衛生管理”の基本
目次
- 1. はじめに
- 2. HACCPとは?―すべての食品関連事業者が対象?
- 3. 飲食店・製造・卸でどう違う?業種別のポイント
- 4. HACCPの基本:7原則12手順をやさしく解説
- 5. 導入のリアル:実例と支援制度
- 6. HACCPと知財・契約・知的資産のかかわり
- 7. おわりに
1. はじめに
こんにちは!
当事務所では、食品事業に関わる小規模な飲食店や製造業、卸売業の皆さまに向けて、知的財産や法務、制度導入の支援を行っています。
今回は、2021年に義務化された「HACCP(ハサップ)」について、飲食店だけでなく製造や卸の立場でも分かりやすく解説します。
2. HACCPとは?―すべての食品関連事業者が対象?
HACCPとは、食品の安全を確保するために、製造・加工・調理の各段階で「危険を予測し、重点管理する」仕組みのこと。
2021年6月から原則すべての食品等事業者に義務化されました。
ただし、一部の例外も設けられており、以下のような業態では営業の届出や衛生管理計画・手順書の作成が不要とされています(※厚労省資料より)。
📝 例外に該当する主な業種:
- 食品や添加物の輸入業
- 常温保存が可能な包装食品の販売業
- 食品や添加物の運搬・貯蔵業(ただし冷蔵・冷凍は除く)
- 合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業
- 器具・容器包装の輸入・販売業
さらに以下のようなケースも、対象外とされることがあります:
- 1回の提供食数が20食未満の給食施設(例:福祉施設の小規模配食など)
- 農家・漁家が行う出荷前の簡易な調製作業(洗浄・選別など)
小規模な事業者は、「HACCPに基づく衛生管理」ではなく「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」として、簡略的な対応でよいとされています。
以下の図が、事業規模や業態ごとのHACCPの適用区分を示しています。
出典:厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html
3. 飲食店・製造・卸でどう違う?業種別のポイント
🍴 小規模飲食店
- 衛生管理計画に基づき、日々の記録を行い、一定期間保存
- 定期的に記録を振り返り、必要に応じて衛生管理計画や手順書を見直すことが求められます
🏭 食品製造業
- 原材料の受け入れから製造・包装・保管までの各工程を詳細に管理
- 加熱温度・異物混入防止・金属探知機使用など、重要管理点(CCP)の設定がカギ
🚚 卸売・運搬業者
- 食品の温度・清潔な輸送環境の維持が求められます
- 保管・配送記録の整備や、クレーム発生時の対応ルール整備も重要
4. HACCPの基本:7原則12手順をやさしく解説
HACCPの導入には、「12手順」で準備を進め、「7原則」に基づく衛生管理を行うというステップがあります。
🔹【12手順(抜粋)】
- HACCPチームの編成
- 製品の特性の記述
- 製造工程一覧図の作成
- 現場確認(バリデーション)
- 危害要因分析(微生物・化学物質など)
- 重要管理点(CCP)の決定
- 管理基準(加熱温度など)の設定
- モニタリング方法の設定
- 改善措置の決定
- 検証手続きの設定
- 記録の作成と保存方法の決定
- 手順の見直しと継続的改善
🔸【7原則】
- 危害要因の分析
- 重要管理点(CCP)の決定
- 管理基準の設定(例:中心温度75℃以上など)
- モニタリング方法の設定
- 改善措置の設定
- 検証手続きの設定
- 記録の作成と保存
中小規模では、必要最低限の項目を実行する「簡略型」での対応が認められており、保健所の指導のもとで無理なく進めることが可能です。
5. 導入のリアル:実例と支援制度
「難しそう」「うちは小さいから関係ない」と思われがちなHACCPですが、実際は商工会や地域団体の支援を受けながら、記録用紙の配布・巡回指導・補助金活用などによる導入が進んでいます。
🍱【導入事例1】小さな惣菜店の挑戦
家族経営の惣菜店が、商工会の支援で衛生記録シートを導入。調理ごとの温度、手洗い、器具の消毒状況などを記録する表を壁に掲示し、スタッフ全員で共有する体制を整えました。
❄【導入事例2】冷凍食品の卸会社
地元の卸売業者が、補助金を活用し、倉庫に温度ロガーを設置。輸送業者とも連携して、食品配送中の温度記録を定期的に保管し、クレーム削減に成功しています。
💰【活用可能な支援制度】
- 小規模事業者持続化補助金(設備導入、販促費も対象)
- HACCP関連の衛生機器導入補助(市区町村や保健所経由)
6. HACCPと知財・契約・知的資産のかかわり
HACCP導入に際し作成されるマニュアル、教育資料、チェックリストなどは、知的財産(著作物)やノウハウ=知的資産として非常に重要です。
これらは、2026年春に施行予定の「企業価値担保権」制度において、企業の“資産価値”として評価される可能性もあります。
また、外部と連携して導入を進める場合は、秘密保持契約(NDA)が欠かせません。
✍️【NDAのちょっとした事例】
たとえば、厨房設備会社に衛生動線の提案を依頼した飲食店が、事前に「社内レイアウト図は外部使用不可」と明記した契約を交わし、ノウハウの流出を防ぎつつ安心して打ち合わせを進められた、という例もあります。
7. おわりに
HACCPは単なる衛生ルールではありません。
それは、お客様に「信頼される事業者」として認識されるための“仕組み”です。
飲食店でも、製造業でも、卸売業でも――
できるところから、始めてみませんか?
\HACCPで守る日常。知財で守る未来。お気軽にご相談ください!/
――おまけ
暑い暑い日が続いていますね。日中外に出るのも億劫になるほど・・・
でも、季節は少しずつですが着実に進んでいるようです
我が家の紫式部もほんのり色づいてきました
 秋のおすそ分け
秋のおすそ分け
📚過去記事はこちら
▶第1回:O-157がきっかけだった ― HACCPとの出会い!
▶第2回:味だけじゃない“見えない価値”も守る― 小さなお店が知っておきたい知的財産リスクとは?
▶第3回:食の安心×知財シリーズ 第3回:見た目で選ばれる時代
🔗参考リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日
お知らせ2025年12月31日2025年大晦日