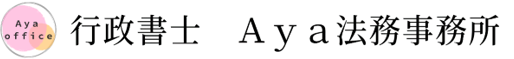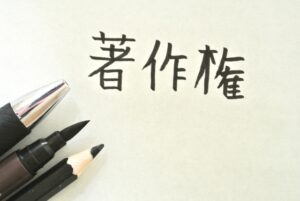🍱食の安心×知財シリーズ第5回:GAPってどういう仕組み?―信頼される農産物づくりとは
目次
- 1. はじめに
- 2. GAPとは?―農場を守る信頼のフレームワーク
- 3. JGAPの歴史と拡大スピード
- 4. GAPの種類と特徴(JGAP/ASIAGAP/GLOBALG.A.P.)
- 5. GAPを取得するメリット
- 6. 導入事例
- 7. 農業者向け支援制度
- 8. HACCPとの関係
- 9. GAPと知的財産・ブランド戦略
- 10. おわりに
1. はじめに
こんにちは!
前回は食品の安全を守る仕組み「HACCP」についてご紹介しました。今回は農業分野に目を移し、「GAP(Good Agricultural Practice/適正農業規範)」を解説します。
GAPは農産物の安全性や環境への配慮、労働安全を確保する仕組みであり、消費者の信頼を高めるだけでなく、農業者自身の経営改善や販路拡大にもつながります。近年では輸出や国際イベントの調達基準としても必須となっており、「農業の未来を支える世界共通言語」と言っても過言ではありません。
2. GAPとは?―農場を守る信頼のフレームワーク
GAPは「良い農業の実践」を意味し、農場での作業を体系的に管理することで、食品安全・環境保全・労働安全を実現する仕組みです。特に国際水準のGAPは次の5分野を網羅します。
- 食品安全
- 環境保全
- 労働安全
- 人権保護
- 農場経営管理
これらはSDGsやESG投資にも直結しており、持続可能な農業の基盤とされています。
3. JGAPの歴史と拡大スピード
2005年に日本GAP協会が設立され、JGAPとして統一されました。農林水産省の最新資料では、2008年から2015年の間に認証農場が約10倍に拡大。令和7年3月末時点では、JGAP・ASIAGAP・GLOBALG.A.P.の合計で7,414経営体が認証取得。さらに、認証は未取得でも「国際水準GAPに準拠した取組」を実践する農業者が53,608経営体に上ります。
4. GAPの種類と特徴(JGAP/ASIAGAP/GLOBALG.A.P.)
- JGAP:日本国内向け。農林水産省推奨で最も普及。
- ASIAGAP:国際規格対応。アジア市場や輸出で有効。
- GLOBALG.A.P.:欧州を中心に世界標準。輸出時に不可欠な場合も多い。
また、「GAPをする」(記録・点検・改善を自ら実践)と、「GAP認証をとる」(外部審査で客観的に証明)は別物。
小規模農家はまずできる範囲の実践から始め、流通拡大や輸出を見据えて認証取得を検討する流れが現実的です。
5. GAPを取得するメリット
- 消費者の信頼性向上:認証マークで安心を訴求
- 販路拡大:スーパーや輸出市場での条件を満たす
- 作業効率化:手順の標準化で事故や無駄を減らす
- 環境保全・労働改善:持続可能な農業経営、人材確保につながる
東京2020大会では選手村の野菜は100%、米は82%がGAP認証済。今後の大阪・関西万博(2025)、アジア大会(2026)、国際園芸博覧会(2027)でも調達基準として採用予定で、国際的にも「信頼の証」として評価されています。
6. 導入事例
📌事例1:地元トマト農家(国内小規模)
ある地方の家族経営のトマト農家は、JGAP認証を取得。以前は直売所や地元市場が中心でしたが、認証により大手スーパーとの契約が実現し、安定的な販路を確保しました。農薬使用量と散布記録を見直すことでコスト削減も達成。作業手順のマニュアル化により、パート従業員も迷わず品質を保てる体制が整いました。
📌事例2:果樹園とASIAGAP(輸出)
ある果樹園は輸出を視野にASIAGAPを取得。国際規格を満たしたことで商社や海外小売からの信頼を獲得し、海外市場に参入しました。従業員研修を通じた作業標準化で、季節雇用の定着率が上がり、収穫時のミスやロスも減少しました。
📌事例3:日本コカ・コーラ株式会社(企業サプライチェーン)
茶系飲料の原料調達においてJGAP認証産地を基盤に活用。自社基準「SAGP」との差分のみ追加で導入できる枠組みを整え、約6,000haの茶産地へ普及。サプライチェーン全体で持続可能な農業を推進した代表例です。(出典:農林水産省「GAP普及大賞2015」)
📌事例4:韓国ノルメインサム(国際展開)
韓国の営農組合法人ノルメインサムは、K-GAPに加えて日本のJGAPや欧州のGLOBALG.A.P.も取得。日本・欧州市場への輸出を拡大し、地域に海外認証支援センターを設立。JGAPハングル版の作成にも尽力しており、国際的なGAP普及の拠点となっています。(出典:農林水産省「GAP普及大賞2015」)
📌事例5:JA北魚沼GAP部会(米づくり)
新潟県のJA北魚沼では、行政と連携して稲作農家にJGAPを普及。定期研修で農家同士がノウハウ共有を進め、導入ハードルを大きく下げました。「安全で信頼できるコメづくり」を地域全体で推進し、ブランド価値の向上にもつながっています。(出典:農林水産省「GAP普及大賞2015」)
📌事例6:団体認証の活用(中小農家向け)
ある地域のJAは個別ではなく団体認証を取得。審査費用や事務負担を大幅削減し、小規模農家でも参加しやすい体制を構築。団体で品質管理を統一することで、取引先からの信頼も強化されました。
7. 農業者向け支援制度
農林水産省や自治体が認証取得支援を実施。補助金で導入費用を軽減でき、JAや普及指導員による研修・巡回指導も充実しています。
まずは「できるところから始める」「記録だけでも続ける」といった小さな一歩が、将来の認証取得や販路拡大につながります。
8. HACCPとの関係
GAP=原材料(農産物)を安全に生産する基準
HACCP=原材料を用いて食品を製造する際の衛生管理基準
一見別の基準に見えますが、HACCPには「原材料の仕入れ」に関する規定があり、できるだけGAP認証を取得した生産者から調達することが望ましいとされます。欧州では既に仕入れ条件として定着。日本でもHACCPの普及に伴い同様の流れが強まる見込みです。
9. GAPと知的財産・ブランド戦略
GAPは「安全の証」であると同時に、ブランド戦略の一部です。
認証マークで消費者に安心を伝え、地理的表示(GI)と組み合わせて地域ブランドを強化。契約・調達条件でも「信頼の証明」として活用できます。
GAPを導入することは、農業者にとって知的資産の蓄積でもあります。
10. おわりに
GAPは農場の日常を変え、未来の農業を広げる仕組みです。消費者にとっては「安心」、農業者にとっては「経営改善と信頼性向上」。双方にメリットがあります。
\GAPで守る農の信頼。知財で守る未来。お気軽にご相談ください!/
📚過去記事はこちら
▶第1回:O-157がきっかけだった ― HACCPとの出会い!
▶第2回:味だけじゃない“見えない価値”も守る― 小さなお店が知っておきたい知的財産リスクとは?
▶第3回:見た目で選ばれる時代― パッケージ・店舗デザインの“知財リスク”と守り方
▶第4回:HACCPって何?飲食店・製造・卸まで―安心をつくる“衛生管理”の基本
🔗参考リンク
参考:農林水産省「国際水準GAPガイドライン解説書」「GAPを巡る情勢」「GAP初級編」、農林水産省「GAP普及大賞2015」各資料
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶