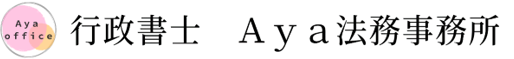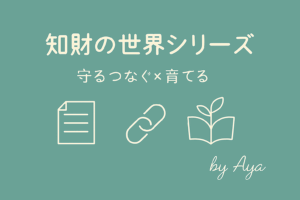情報セキュリティと知財管理シリーズ第4回:クラウド時代の情報漏洩防止術
―個人端末・LINE・SNS・メールの危険と対策
こんにちは!
クラウドやSNSが当たり前になった今、「情報漏洩の心配は大企業だけの話」…と思っていませんか?
実は、中小企業や個人事業主、そしてフリーランスの方でも、日常のちょっとした油断から情報が漏れてしまうことが増えているんです。
今回は、実際にあった事例や対策を交えながら、今日からできる情報漏洩防止のポイントをお話しします。
クラウド時代に急増する情報漏洩リスク
クラウドサービスは便利ですよね。ファイル共有やデータのバックアップも簡単で、仕事がはかどります。
でも、アクセス権限をきちんと管理していなかったり、共有設定を誤ってしまうと、社外の人でも大事な資料にアクセスできてしまうことがあります。
実際、ある会社ではプロジェクト資料をクラウドにアップしたまま「全員に公開」設定になっていて、検索エンジンから丸見えになっていた…なんてこともありました。
個人端末・LINE・SNSの危険性
私物端末で業務データを扱うリスク
自分のスマホやタブレットで仕事のデータを扱うのって、やっぱり危ないんです。
例えば、通勤中にスマホを落としてしまってロックが甘かった場合、誰かが中の業務データを見られる可能性があります。
家族とアカウントを共有しているケースでも、知らないうちにデータがコピーされてしまうこともあります。
LINEやチャットアプリの誤送信
急いで送ったメッセージ、送信先を間違えてヒヤッとしたことありませんか?
特にLINEグループでは、外部の人が混ざっていることに気づかず社内情報を送ってしまう事故が実際にあります。
SNS投稿からの間接漏洩
SNSに何気なくアップした写真に、会議の資料やホワイトボードの内容が写り込んでいた…
これも立派な情報漏洩です。背景や画面に要注意です。
メールを介した情報漏洩リスク
最近はフィッシングメールの手口が本当に巧妙です。
取引先や同僚を装って「請求書送付の件」なんて件名でメールを送ってきます。
添付ファイルを開くと実はウイルスだった…なんてことも。
実際、ある企業では経理担当者が正規の請求書だと思ってPDFを開き、結果的に社内ネットワークが感染。顧客データが外部に送信される被害が発生しました。
私が以前勤めていた会社では、「もし開いてしまったらLANケーブルを抜く・Wi-Fiを切る・担当部署へ連絡」という初動対応が徹底されていて、大きな被害は防げました。
業務ツール使用時の注意点
無料のクラウドや外部連携ツールは魅力的ですが、設定をよく確認せず使うと危険です。
アクセス権限が甘いまま外部サービスとつなげると、第三者がデータを見られる可能性があります。
設定ミスによる情報漏洩の実例
- 共有リンクを「誰でもアクセス可能」にしてしまい、検索で見つかる状態になっていた
- 期限なし・パスワードなしの共有リンクが外部に転送されていた
今日からできる情報漏洩防止の5つの対策
- 端末とアカウントの二重ロック
- 業務用と個人用アカウントの分離
- 共有リンクには期限・パスワード設定
- 新しいツールは規約と設定を必ず確認
- 定期的な研修やミーティングで意識向上
よくある質問(FAQ)
Q1. 情報漏洩はクラウドを使わなければ防げますか?
A. いいえ。クラウドを使わなくても、USBやメール、紙資料などから漏洩します。
Q2. フィッシングメールを誤って開いてしまいました。まず何をすべき?
A. すぐにネットワークを遮断し、電源は切らずに情報システム担当へ報告してください。
まとめ・ご相談のご案内
クラウドやSNS、メールは業務効率化の武器ですが、使い方を誤れば大きなリスクになります。
今回ご紹介したポイントを押さえて、日常から「情報を守る習慣」を作っていきましょう。
当事務所では、中小企業・個人事業主の情報管理体制づくりをサポートしています。 お気軽にご相談ください。
📚過去記事はこちら
・第1回:技術流出で書類送検!営業秘密の持ち出し事件から学ぶ、企業が取るべき情報管理対策とは?
・第2回:NDA(秘密保持契約)で本当に情報は守れる? 基本条項と見落としがちな落とし穴を解説!
・第3回:裁判で「営業秘密と認められなかった」実例に学ぶ
🔗外部リンク
▶独立行政法人 情報処理推進機構セキュリティセンター:情報漏えい発生時の対応ポイント集
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説
著作権2026年1月19日【著作権の基礎シリーズ:第2回】複製権ってなに?身近な“コピー”のルールをやさしく解説 著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの?
著作権2026年1月12日【著作権の基礎シリーズ:第1回】著作権にはどんな権利があるの? お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月1日新年のご挨拶 お知らせ2025年12月31日2025年大晦日
お知らせ2025年12月31日2025年大晦日