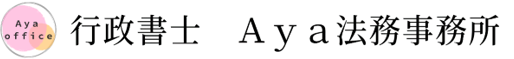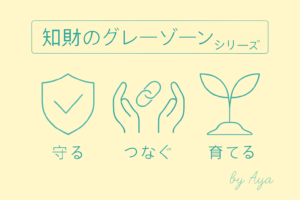4つの枠でチャンス拡大!補助金を使って後継者問題・M&Aの費用を支援
2025年度『事業承継・M&A補助金』最新活用術
中小企業、小規模事業者、個人事業主の皆様、2025年度(第13次公募)「事業承継・M&A補助金」は、事業の未来を左右する「次の一歩」を強力に後押しする制度です。
後継者への承継、M&A、廃業、再出発など、事業転換には専門家費用や設備投資など多額の費用が伴います。「資金が不安で一歩踏み出せない…」と悩む経営者にとって、返済不要なこの補助金はまさに追い風となります。
本記事では、公募中の「4つの枠」の特徴と活用ポイントを、具体的な事例を交えて徹底解説します。自社に最適な枠を見つけ、申請準備をすぐに始めましょう。
この記事の目次
■ 事業承継・M&A補助金とは
中小企業や小規模事業者、個人事業主の方々が、後継者問題・M&A(合併・買収)・廃業・再出発といった「次の一歩」を踏み出す際、費用の一部を国が支援してくれる制度が「事業承継・M&A補助金」です。
多くの事業者が「承継したいが資金が…」「M&Aの準備段階から手が回らない」「廃業の整理にもお金がかかる」と悩む中で、この補助金は「新たな挑戦を後押しする」役割を担っています。
例えば、専門家に支払う手数料、機械設備の入れ替え、店舗・事務所の改装、在庫処分・解体費用など、実務的に発生するコストを“支援対象”とする枠が設けられています。
この補助金を活用することで、借入れに頼るだけでなく、返済不要な支援を受けて安心して次のフェーズへ進める可能性が広がります。
4つの枠で自社のニーズをチェック!活用ポイントと目安
以下、2025年度(第13次公募)で募集されている「4つの枠」について、それぞれの特徴と、活用する際のポイントを整理しました。
| 枠の名称 | 目的・対象となる事業 | 補助上限の目安 | 補助率の目安 |
|---|---|---|---|
| ① 事業承継促進枠 | 親族・従業員などへの事業承継に伴う設備投資や改築費用 | 800万円~1,000万円 | 小規模:2/3、一般:1/2 |
| ② 専門家活用枠 | M&Aの準備・実行にかかる専門家費用(仲介、FA、弁護士等) | 600万円~2,000万円 | 1/2~2/3程度 |
| ③ PMI推進枠 | M&A後の経営統合(PMI)にかかるIT化、組織再編費用 | 150万円~1,000万円 | 1/2(小規模:2/3)程度 |
| ④ 廃業・再チャレンジ枠 | 廃業(清算・整理)または再チャレンジ(新規創業準備)費用 | 150万円 | 1/2~2/3程度 |
■ ① 事業承継促進枠
こちらは、親族内承継や従業員承継など、“身近な後継者”に事業を引き継ぐケースを対象とし、設備投資や事務所・店舗の改築といった再構築費用を補助する枠です。
- 補助上限・補助率の目安:
- 通常は上限 800万円。一定の賃上げ要件を満たす場合、上限が 1,000万円に引き上げ。
- 補助率として、小規模事業者の場合は2/3、一般の中小企業でも1/2程度が目安。
- 活用ポイント: 後継者が既に決まっており、事務所改修や機械更新、店舗移転など「新たなスタートを切る準備」ができている場合に有効です。特に、世代交代にあたり、「次の時代に合った体制に整えたい」という事業者に最適です。
- こんな事例あり:
例えば、地域の印刷業で代表交代を機に設備をフル更新、事務所をオープンスタイルに改装して新規顧客を取り込んだケース等
■ ② 専門家活用枠
M&Aを検討する売り手・買い手双方が、FA(フィナンシャル・アドバイザー)、仲介業者、弁護士・会計士などの専門家を活用する際にかかる費用を支援する枠です。
- 補助上限・補助率の目安:
- 補助上限は類型により600万円~800万円。ただし、特定の要件を満たすと最大 2,000万円まで加算される場合がある。
- 補助率は類型によって異なりますが、典型的には1/2~2/3など。
- 活用ポイント: M&Aそのものを“実行段階”に進める準備として、専門家を巻き込んでおきたい場合に有効です。仲介手数料、デューデリジェンス費用、契約書作成費用など、実務にかかる大きなコスト負担を軽くできます。
- こんな事例あり:
例として、売り手企業が解体工事を手掛けていた建設業者。将来を見据えて大手建築会社との提携を模索し、専門家を交えてM&A交渉を進めた結果、売却・統合が実現したケース。
■ ③ PMI推進枠
こちらは、M&A後の経営統合(PMI=Post Merger Integration)に関わる支援に特化した枠です。「買った後どう活かすか」というシナジー創出や組織・仕組みの再構築フェーズに着目しています。
PMI(Post Merger Integration)とは?
M&Aの「その後」に焦点を当てた重要なフェーズが、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)です。直訳すれば「合併・買収後の統合」。これは、単に会社を買った・売ったという“取引”で終わらせず、以下のような実務面の調整を通じて「相乗効果(シナジー)」を生み出すことを目指します:
- 業務フローや社内制度の統一
- 組織文化・風土のすり合わせ
- 会計・システム・IT基盤の統合
- ブランド・販売チャネルの再構築
- 人材の定着と再配置
PMIが適切に進められない場合、「買収したが業績が悪化した」「社員が辞めた」「業務が混乱した」といった失敗につながることもあります。
そこで、「PMI推進枠」ではこのPMIにかかる費用(専門家の支援や設備改修、IT導入など)を支援してくれる仕組みとなっています。
- 補助上限・補助率の目安:
- 「PMI専門家活用」の上限は 150万円。
- 「事業統合投資」の上限は 800万円(一定の賃上げ要件を満たすと1,000万円)。
- 補助率例としては1/2(小規模事業者であれば2/3)程度。
- 活用ポイント: M&Aを機に業務プロセス整備、人材育成、IT化、組織統合などを実施する場合に力になります。
- こんな事例想定:
たとえば、製造業A社が部品加工メーカーを買収し、両社の生産ラインを統合。IT基盤を共通化し、販路を共有して売上を拡大した。こうした「買って終わりにしない」統合計画を伴ったケースで活用されています。
- 補助上限・補助率の目安:
■ ④ 廃業・再チャレンジ枠
事業承継やM&Aが難しい状況にある事業者が、廃業を選択ないしはリセット(再チャレンジ)を視野に入れて、「清算」「整理」「再出発」のために要する費用を支援する枠です。
- 補助上限・補助率の目安:
- 補助上限は概ね 150万円。
- 補助率は約1/2~2/3といった水準。
- 活用ポイント: 店舗撤退・在庫処分・解体・設備撤去など、廃業に際して発生する実務コストを補助します。再チャレンジ(新規創業準備)を考えている場合も、新たな創業準備にかかる経費が対象になる可能性があります。
- こんな事例あり:
地域の小売店が後継者不在で閉店を決め、店舗設備を撤去・在庫を処分して次のビジネスを立ち上げた際、この枠を活用して廃業費用の一部を補助されたというパターンがあります。
- 補助上限・補助率の目安:
事例で振り返る活用のリアル
制度の説明だけでなく、実際の公的事例からイメージを深め、自社の状況と照らし合わせてみましょう。
・事例1:卸売業・小売業 A社(専門家活用 × 買い手支援型)
後継者不在かつ人口減少地域の薬局を営むA社。地域のインフラとしての店舗継続性を重視し、仲介業者を通じて別法人へのM&A交渉を進めた。
活用枠:専門家活用枠
ポイント:「地域インフラを残したい」「後継者がいないから別法人が引き継ぐ」という、地域と事業の継続性を重視するケースにマッチ。
・事例2:建設業 B社(専門家活用 × 売り手支援型)
設立4期目の解体工事業B社。「事業の展開幅を広げたい」との視点から、大手建築会社を買い手候補にM&A交渉を実施。提携によるシナジーを狙った。
活用枠:専門家活用枠
ポイント:売り手が「次の成長を見据えて身軽になる」「提携でシナジーを出したい」と考えている場合に有効。
・事例3:組織統合を経た製造業(PMI推進想定)
製造業者が部品加工会社を買収。買収後、IT化・生産ライン統合を推進することで、短期間で売上拡大・コスト削減を実現。
活用枠:PMI推進枠
ポイント:「買って満足」ではなく、「買った後どう生かすか」という統合計画に力を発揮。
活用時の注意点・チェックリスト
補助金を「申請して終わり」ではなく、交付・実行までスムーズに進めるために、以下のポイントを押さえておきましょう。特にGビズIDの取得は時間がかかるため、早めの対応が鍵となります。
- 最新の『公募要領』を必ず確認する : 第13次公募では4枠すべてで募集が出ています。
- 「GビズIDプライム」の早めの取得 : 発行まで時間がかかるため、申請前に対応が必要です。
- 補助対象経費の範囲を確認 : 枠ごとに異なるため、何が「対象経費」になるかをしっかり確認しましょう。
- 実績報告・証拠書類の提出 : 交付決定後には必須です。期限や形式を守らないと返還の可能性もあります。
- 補助率・上限の条件を整理 : 自社の規模、従業員数、賃上げ実績などを事前に整理し、条件を満たすかチェック。
- 最重要!実現性の検討 : 補助金を活用することが、事業計画・資金計画を含めた将来の事業展開にとって本当に有益か、冷静に検討した上で申請を判断しましょう。
まとめ:次の一歩を後押しする支援制度
この制度は、事業を「継続」するためだけでなく、「次のステージに成長させる」「再チャレンジを支援する」「事業を安心して引き継ぐ」ための支援だととらえると、活用の選択肢が広がります。
- 後継者が決まっていて設備更新・体制整備が必要な方 → 事業承継促進枠
- M&Aを含め専門家を交えた交渉を進めたい方 → 専門家活用枠
- 買収後の統合作業まで含めて成長を描きたい方 → PMI推進枠
- 廃業を考えていた/次のビジネスを視野に入れている方 → 廃業・再チャレンジ枠
まずは「自社がどの枠に当てはまるか」「どんな支援が必要か」を整理し、申請に向けての準備(特にGビズIDプライムの取得)を早めに進めてみてください。
補助金申請は準備が鍵!Aya法務事務所にご相談ください
補助金申請には「準備」が鍵となります。まずは社内で現状を整理し、どの枠に該当するかを確認しましょう。
ご相談・無料診断(必要書類チェックや該当枠アドバイス)など、お気軽に Aya法務事務所までご連絡ください。
Aya法務事務所は、認定経営革新等支援機関として登録されており、補助金申請に必要な事業計画の作成支援や確認書発行にも対応可能です。初めてのご相談でも、丁寧にヒアリングを行いながら進めますので、安心してご相談ください。
📚関連ブログ
▶情報セキュリティと知財管理シリーズ第9回:補助金申請にも関係?―情報館態勢が評価される時代へ―
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。