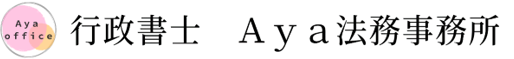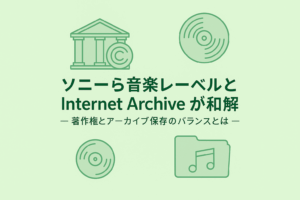知財のグレーゾーンコラム①(第1.5回):営業秘密と契約の穴
〜守ったつもりが、守れてなかった〜
こんにちは。
今回のコラムでは、第1回で取り上げた「営業秘密」について、契約書の観点から見た注意点を掘り下げてみたいと思います。
▶第1回:営業秘密が漏れる典型パターンと防止策を解説!
目次
💥 実は“守れてなかった”実例
「ちゃんと秘密保持契約(NDA)を結んだから大丈夫」
そう思っていたのに、いざトラブルになったら守られなかった――
そんなケースは、決して珍しくありません。
――たとえば、こんなケースが実際にあります。
📂 ケース1:NDAはあるけど、ザル管理だった
開発業務を委託した外注先とNDAを結んでいたが、秘密情報ファイルにパスワードが設定されておらず、誰でも閲覧可能な状態だった。
→ 秘密管理性が認められず、「営業秘密」としての保護を受けられなかった。
🚪 ケース2:契約書に「秘密保持義務期間」の定めがない
退職した元社員が社内ノウハウを別会社に提供していた。
しかし、雇用契約書に秘密保持の条項はなく、NDAも未締結。
→ 元社員の行為に法的な制限をかけることができなかった。
🔍 契約で見落とされがちな5つの「穴」
① 秘密情報の定義があいまい
「秘密情報」として何を対象にしているかが不明確だと、後で「それは含まれていない」と主張されてしまうことも。
🛠対策:
「営業上、技術上その他業務上の情報のうち、文書に『秘密』と表示されたもの、または開示時に口頭で秘密と指定されたもの」などと具体的に記載を。
② 契約だけあって、社内の管理が不十分
NDAを結んでも、実際にアクセス制限や権限管理がなされていないと、秘密管理性が否定されてしまいます。
🛠対策:
「秘密情報の保存・管理に関する社内ルール(例:パスワード管理、閲覧権限、廃棄時の手続き)を整備し、実際に運用する」ことが不可欠です。
③ 秘密保持義務の期間が適当(または未設定)
契約終了後も秘密は守られるべきですが、条項がなければ期限が曖昧に。
🛠対策:
「契約終了後も○年間秘密保持義務を負う」と明記するのが基本です。
④ 目的外使用の禁止が書かれていない
契約上、秘密情報を「第三者に漏らしてはいけない」と書かれていても、自社での“想定外の使い方”が禁止されていないケースがあります。
🛠対策:
「秘密情報は、本契約に基づく業務遂行の目的の範囲内でのみ使用するものとし、他の目的に使用してはならない」
といった文言を明記しましょう。
⑤ 契約終了後の情報返却・廃棄の定めがない
契約が終わっても、相手の手元に秘密情報が残り続けることはよくあります。
このままだと「まだ保持していてよい」と思われてしまい、情報漏えいの原因に。
🛠対策:
「契約終了時には、秘密情報を返却または廃棄し、その旨を書面で報告すること」と明記しておくのが安心です。
🧭 NDAに頼りきらない「営業秘密」の守り方
契約書はもちろん大事ですが、それだけでは守り切れません。
重要なのは、「契約+社内運用」で一体的に管理することです。
たとえば…
| 項目 | 実務対応例 |
|---|---|
| 秘密情報のラベル付け | 「社外秘」などの表示をファイル名・文書上に明記 |
| 退職時の対応 | 秘密保持に関する誓約書を再取得、情報返却の確認 |
| 委託先管理 | 情報へのアクセス制限、契約書チェックリストの活用 |
📝 おわりに
NDAや契約書は「備え」としてとても重要ですが、
“契約を交わすこと”が目的になってしまっては意味がありません。
契約と運用のバランスを取りながら、
「ちゃんと守れているか?」を定期的に見直していくことが、
トラブルを防ぐ何よりの近道です。
私もまだまだ勉強中ではありますが、「知らなかった」で困る方を少しでも減らせるよう、
これからも知財のことを、できるだけわかりやすく発信していきます。
また気が向いたときに、のぞいていただけたら嬉しいです。
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちら
🔗外部リンク
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに?
著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに? 相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは?
相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは? 著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は?
著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は? 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説