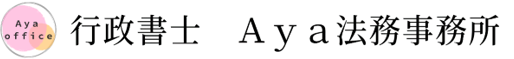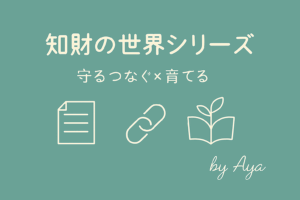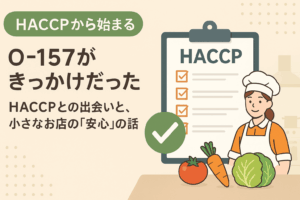情報セキュリティと知財管理シリーズ第2回:NDA(秘密保持契約)で本当に情報は守れる?
―基本条項と見落としがちな落とし穴を解説!
こんにちは!
当事務所では、個人事業主や小規模事業者の皆さまの知財(知的財産)に関するお悩みをサポートしています。
私自身も日々勉強を続けながら、「ちょっと難しいけれど、全然できなくもない!」を合言葉に、皆さんと一緒に学んでいけるブログを目指しています。
企業秘密やノウハウ、顧客情報を守る手段として、多くのビジネスシーンで使われる「NDA(秘密保持契約)」。
でも…
NDAを結んだから安心!本当にそうでしょうか?
今回は、NDAの基本から、ありがちな誤解や見落としポインをご紹介します。
NDAって、どんな契約?
◆ NDA(秘密保持契約)の目的とは?
- 秘密情報の漏洩や不正利用を防ぐ
- 開示する側の立場を明確にする
- 契約違反時の責任追及のための根拠になる
◆ NDAが使われる具体例
- 新製品・技術の共同開発
- 業務委託や外注時の情報共有
- M&Aや業務提携の初期交渉段階
- 採用活動(職務情報や人事制度)
NDAの基本条項をおさえよう
NDAは実務でもよく使われますが、内容によって効力が大きく変わります。
✅ 1. 秘密情報の定義
何が「秘密」にあたるかを明示的に記載。例:技術資料、見積書、顧客名簿など。
✅ 2. 使用目的・取り扱い範囲
「この範囲ならOK、ここから先は禁止」と線引きが必要。
✅ 3. 有効期間・守秘義務期間
契約期間だけでなく、「契約終了後●年間は秘密保持」などの記載が重要です。
✅ 4. 例外条項
既知の情報、公知情報、法令により開示が求められる場合など。
✅ 5. 違反時の対応
損害賠償、差止請求の明記が必要です。
よくある誤解と見落としポイント
⚠️ NDAがあれば万全…ではない!
- あまりに広すぎる定義は「不明確」として無効になる可能性も
- 実際の情報管理(アクセス制限、持出制限)が伴わなければ無力
⚠️ 曖昧な合意はNG
- 口約束、メールだけの合意、署名・押印がないケース
- 条件が一方的に偏っている契約書は相手に拒否されることも
NDAは「契約」+「実務管理」で守るもの
契約を結ぶだけでは十分ではありません。
- 社内のアクセス制限・閲覧制限
- データへのパスワード保護、持出制限
- 退職・転職時の誓約書や面談
情報を守るには、日頃の運用とセットで考える必要があります。
まとめ:NDAはスタート地点。守るための仕組みをセットで考えよう
NDAは、情報を守るための「入口」であって「万能薬」ではありません。
契約書の内容を理解し、日頃の管理体制と合わせて運用することで、初めて大切な情報が守られるのです。
このシリーズの他に、知財シリーズや著作権シリーズでも色々な事例を交え展開中です。興味があれば、是非読んでいただけると嬉しいです!
知財をもっと身近に。もっと味方に。
\お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!/
📚過去記事はこちら
・第1回:営業秘密の持ち出し事件から学ぶ、企業が取るべき情報管理対策とは?
🔗関連リンク(外部サイト)
✅ 中小企業庁:知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について
▶ 次回は【コラム①】裁判で「営業秘密と認められなかった」実例をご紹介します。
投稿者プロフィール

- 皆様のお役に立てる情報をお届けしたいと思っております。
最新の投稿
 著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに?
著作権2026年2月9日【著作権の基礎シリーズ:第5回】公衆送信権ってなに? 相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは?
相続2026年2月6日2026年2月2日スタート|不動産記録証明制度とは? 著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は?
著作権2026年2月2日【著作権の基礎シリーズ:第4回】家でDVDを見るのはOK?上映会は? 著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説
著作権2026年1月26日【著作権の基礎シリーズ:第3回】上演権・演奏権とは?身近な例でやさしく解説