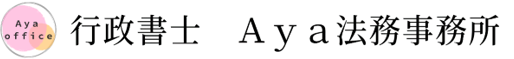知財のグレーゾーンシリーズ第2回:不正競争防止法の落とし穴
――「盗用された!」と思っても守れないこともある?
目次(クリックでジャンプ)
- はじめに:盗まれた!…でも守られない?
- 不正競争防止法ってどんな法律?
- こんな落とし穴に注意!3つの事例
- 罰則・損害賠償などの救済措置
- 実は守られない「正当取得」のケース
- まとめ:不正競争防止法を味方にするには?
- 過去記事・外部リンク
はじめに:盗まれた!…でも守られない?
起業や副業を始めると、「これ、自分のアイデアだったのに」「まさか、あの人が…」という場面に出くわすことがあります。
たとえば──
- オリジナルで考えたサービス名やロゴを、よく似た形で他社が使っていた
- 商談や打ち合わせで話した内容が、なぜか別の会社から先に発表された
- SNSに投稿した自作のレシピや作品画像が、無断で別アカウントに転載されていた
こうしたケースは、まさに“盗用された”と感じる瞬間です。
しかし、残念ながら日本の法制度では、「パクリ=即違法」とはなりません。 相手の行為が法的に“アウト”かどうかは、非常に細かい要件や証明の難易度が絡んでくるのです。
特許や著作権などの“登録型”の知財ではない、「不正競争防止法」という法律も、ある意味グレーゾーンを守る頼れる存在。 ただし、万能ではありません。使える条件があるのです。
この記事では、「何が守られて」「何が守られないのか」―― グレーゾーンの現実を、豊富な事例と共に、読み応えたっぷりにお伝えします。
不正競争防止法ってどんな法律?
「不正競争防止法(略して“不競法”)」は、その名のとおり、ズルを防ぐ法律です。 でも、ズルにもいろいろありますよね。
この法律がターゲットにしているのは、たとえば次のような行為です。
- 元社員が会社の顧客リストを持ち出して、新会社で営業をかけた
- 有名になったロゴやキャッチコピーを、他社がそっくり使って商品を販売
- SNSで人気になったレシピをそのままコピーして、商用サイトに掲載
- まだ発売前の商品を撮影して、ライバルが先に模倣して販売した
これらは、いずれも「不正な手段で他人の努力を利用する」ことにあたります。 つまり、企業やクリエイターが積み上げてきたブランド・信頼・ノウハウなどの“無形資産”を守る法律なのです。
特徴的なのは、登録がなくても使える点。 特許や商標は出願・登録が前提ですが、不競法は実態があれば使える“現場型”の武器ともいえます。
ただし、それだけに「これは不正だ!」と主張するには、要件や証拠がとても厳格です。 このあとの章で、実例とともに“落とし穴”を掘り下げていきます。